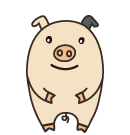小さな国語塾のつぶやき
鑑みる
[人は流水「に」鑑みる莫くして、止水「に」鑑みる(ひとはりゅうすいにかんがみるなくして、しすいにかんがみる)意味:人は誰でも、流れる水ではなく穏やかな水に自分を映す]「明鏡止水(邪念がなく、澄み切って落ち着いた心の形容)」のもとになった孔子の言葉である。ちなみに「鑑みる」の「鑑」は本来、「鏡」という意味がある。さて、上記の文章を見ると分かるように「~に鑑みる」が正しい使い方なのだがビジネス書などでは時々「~を鑑みて・・・・」と書いてあることが。「鑑みる」とは、単に「〜"を"考える」という意味ではなく「(過去の例・手本)"に"照らして考える」というのが本来の意味なので実は「~を鑑みる」は誤用。なぜ「~を」を間違って使う人が多いのか?おそらく「鑑みる」を単純に「~を考える」と思い込みやすいからだろう。実は「~に照らし合わせて、がすっぽりと抜けているのである。「鑑みる」という難しい言葉を使うだけで上等!とは思わずに、折角、難しい言葉を使うことに挑戦するならばぜひとも正しい使い方を覚えて使いたいもの。ちなみに「鑑みる」という漢字の読みは中学1年生で学習する。
2016/04/12 13:17
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
浮世
中学生の勉強では「浮世草子」「浮世絵」といった「浮世」という言葉が出てくる。自分が中学生だったころ、字を見て「世の中から浮く・・・・」→「フワフワしている」→「楽しい世の中」。つまり「浮世草子」とは「楽しいお話」、「浮世絵」は「楽しい、興味深い絵」と思い込んでいたが・・・ところがそうなると「浮世離れ(世の中の常識から外れている)」の説明がつかなくなる。皆は「浮世」の本来の成り立ちや意味をご存知だろうか?「浮世」とは元は「憂き世」の意で仏教的厭世観から、いとうべき現世。つらいことの多い世の中。無常のこの世を指す。実は「楽しい世の中」の真逆であった。では、なぜ「憂」の代わりに「浮」が用いられるようになったか(←全く紛らわしい~~~)、本来は、形容詞「憂(う)し」の連体形「憂き」に名詞「世」の付いた「憂き世」であったが、漢語「浮世(ふせい)」の影響を受けて、定めない人世や世の中をいうように変化し、「浮き世」と書かれるようになったらしい。漢字は表意文字だからといって、字そのままの意味で解釈するととんでもない誤解を招くことがあるという一例。ふーっ。迷ったりあれ?と疑問に感じた時はすぐに調べることがベスト。
2016/04/11 10:05
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
学校、塾、予備校
最近思うこと・・・。世の中には教育の場として①学校②塾③予備校があるがこの違いや役割は?!学校は基礎的知識を教えて、さらには集団生活を送ることによって社会性を身につける場所、予備校は「受験勉強」をメインに裏技や話術を駆使して生徒たちに教える場所。優秀な予備校講師と言うのはまさにエンターテイナーだと言える・・・と勝手に自分なりに定義してみた。では②の塾の役割は?単純に言うならば①学校③予備校の中間、具体的に言うと生徒たちに勉強の楽しさややりやすさを教えつつ、生徒のことをしっかりと見て声掛けをすることか。学校は1クラス30~40名、先生は教科指導以外にも部活動や少年団の指導、職員会議などなどであまりにも忙しく、それらを見ている生徒たちは遠慮して「親は学校の先生に質問するように言うけれど、なんとなく出来ない」という声を聞くことも。また、逆に一人ひとりのことをじっくりと見て声掛けをしようと思っていてもなかなかそうはいかない現実が。それに対して塾はよほどのマンモスでない限りクラスの人数が学校のクラスよりも少なく、どの塾の先生も生徒たちのことをしっかりと観察しているなあと感じる。自分自身も一人ひとりの様子や態度を観察して、適切なアドヴァイスや声掛けをしたいと心がけている。学校、塾、予備校それぞれの役割があり、たとえ小さな塾でも出来ることがあると思い、これからまた新しい一歩を踏み出そうと張り切っている。
2016/04/10 13:01
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
柔軟な発想
今週の授業では小中学生共に、昨日ブログで紹介した「斬新な表現」演習を行った。前もって例文が20近くあるプリントを準備し、心情を表す表現を自分で記入してもらった。例えば次のような例文がある。●忘れ物を持ってきてくれた母に対して( )。●好きな人の前で大失敗をしてしまい、( )。この( )に心情を表す文を入れるのだが、「とても、すごい、嬉しい、悲しい」などを単独で使ってはいけないという制約付き。最初は「無理~」と言っていた中学3年生のS君だが、二つ三つやっていくうちに「これ、意外と面白いかも!」と次から次へと「おおっ」と思えるような文章を考えついた。先の例文には「忘れ物を持ってきてくれた母に対して(将来、必ず親孝行をするよと心の中で誓った)」「好きな人の前で大失敗をしてしまい、(顔から火が出るようだった)」。さすがに中学生はS君のみならず、どの子も具体的で、成程~と思わせる内容が多かった。それに対して小学生は「心が明るくなった」「ずっしりと重い緊張感」と言った具合に短いながらも素直で素敵な表現が多く飛び出した。子供たちの頭の柔軟さを垣間見ることが出来、今後がますます楽しみにだなあと感じる一週間であった。本当にありがたいことである。
2016/04/09 16:19
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
斬新な表現
今日は各地で始業式、入学式が行われており、皆期待と不安でいっぱいの新年度を踏み出している。国語塾も今日からブログを再開し、授業の方は昨日から新年度のスタートを切り、ワクワク感でいっぱいである。さて、新年度につきものなのが「一年間で頑張りたいこと」作文。読書感想文などとは違って字数制限がない場合が多いが、それでも意外と頭を悩ます課題。この時にぜひ心がけてほしいのが「ありきたりの表現を避けて、少し大げさな表現にすること」!そんなことを言われてもピンと来ないだろうが・・・。例えば、小説では作者のオリジナルの表現のオンパレード!例えば「胸がブツブツと湧き上がってきた」「自分の身体が透明になるのが分かった」などなどと表現されており、これらを分かりやすく説明するという設問が実際に出される。前後から答えは「不安感が湧き上がってきた」「モヤモヤしていたわだかまりがすっかりなくなった」だが・・・・漠然と何となく理解では出来るのだが、完全解答に行きつくのは難しく、だからこそ小説は難解と言える。それを自分が文章を書く時に逆手に取ることをお勧めする。つまり、単純に「頑張ろうと思う」と書くよりも「心を刷新して新しい年を迎える」と言った具合に。この具体例は少々固いが、お気に入りの小説や文章を参考に新しい書きぶりに挑戦してみる一年を迎えてほしい。
2016/04/08 14:48
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
サラダ味
世の中には「知らなかった~」ということが数多くある。そのうちの一つが、お菓子の「サラダ味」。幼い頃から、江崎グリコのプリッツ「サラダ味」や亀田製菓の「ソフトサラダ」というお煎餅を好んで食べているのだが、何度食べても「サラダ味」とは思えず、塩味しかしない・・・。色んな日本語を和製英語として表記することが多い今日この頃、その影響で「サラダ」と名付けたのかと思いきやそうでもなさそうだし・・・と思っているうちにどうでもよくなって忘れていた。たまたまひょんなことから「サラダ味」の意味を知り、長年の疑問が解けた。①実は「サラダ味」とは「サラダ油」をまぶしたお菓子に塩をまぶしたもの。つまり「サラダ+塩味」のこと②「サラダ」の語源はラテン語で「塩」の意味、単に塩味と表記するよりもおしゃれに「サラダ味」と表記した・・・などの由来がある。何気に確認してみると、最近ではプリッツにもソフトサラダ煎餅にも小さく「塩味」と記載されているが、それでも「サラダ味」と見ると誤解する人も多いだろう。そこでメーカーにお願いしたい!味の説明や語源、由来を裏面にでもいいのでちょこっと説明書きを入れてほしい、と。いやはや、本当に言葉って難しい。※月曜日~木曜日まで諸所の事情からブログはお休み。金曜日から再開するのでお楽しみに~?!
2016/04/03 14:21
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
真似できる才能
何気にネットを開くと興味深い記事が。「同じ天才でも信長と家康には違いが」というタイトル!言うまでもなく信長は、織田信長、家康とは徳川家康で、誰もが名前を聞いたことがある武将の名前。さて、この記事では二人の違いを「家康は、自分をどんどんと進化させていくところ」だ指摘。信長と言えば「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」と後年に表現されるぐらいに短期な性格だったとされている一方で、家康が「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」とあるように辛抱強い性格とされている。が、家康が短気ではなかったのかというと…実は本質的には短気な性格だったらしいというエピソードが記事に書いてあった。つまり元々の気質は二人とも短気だったのだが、家康は「短気は損気」とばかりに自らの短気を押さえるべくして努力した点が素晴らしいのだ。さて、以前にも何度も書いているが「学ぶ」の語源は「真似ぶ」、つまり素晴らしい人や物をまずは真似ることが大切!でも、真似ることのできる「才能」と真似ることが出来ない「才能」があると思う。例えば、織田信長の天才的な独特の発想はまさに天から与えられた「天賦の才」で後天的に身につけたものではないだろうから簡単に「真似る」ことは難しい。が、家康の「自分をどんどん進化させていく」という姿勢は真似ることが出来る才能の一つと言えるのではないか?新年度が始まったばかり、周囲の良い習慣や才能をどんどん真似て学んでいこうと決意を新たにしている。
2016/04/02 16:26
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
新聞社の持ち味
今日から新年度。子供たちは学年が一つ上がり、会社では新入社員が入ってきたり新しい勤務地で・・・という方もいるだろう。さて、新聞紙上では朝日新聞においては一面一番下のコラム「天声人語」の執筆者が代わると紹介があった。二人体制で執筆しているようだが毎回担当者の名前が記載されているわけではない、お二人ともプロ中のプロなので毎日楽しく時事、文章の勉強をさせてもらっている。それに対して地元の新聞である「十勝毎日新聞」の一面下段の「編集余禄」は執筆者が複数名、時には素人さん?と思う方が担当しているようでそれはそれで面白い。先入観を持たないようにと、本文を読んでから(時には途中で放棄することも・・・・汗)最後に執筆者を確認する。そうすると「お!?今日の文章は素晴らしい!」と感じる日の執筆者は大抵同じ・・・。単に文章の好みと言われればそれまでなのだが、執筆者の名前が書いてあったり、複数で担当しているからこその読者の楽しみもある。どちらが良い悪いではなく、それぞれの新聞社の持ち味を今後も生かしながら紙面づくりをしていただきたいと「新聞大好き」人間としては切に願う。
2016/04/01 13:51
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「けふ」「てふ」
歴史的仮名遣いはと現代仮名遣いは若干異なり、小学生のうちは塾などで、中学生になると学校の授業で「ハ行」は「ワ行」、「ゑ、ゐ」は「え、い」、「ぢ、づ」は「じ、ず」と表記することを習う。もう少し高度な読み方に「けふ」「てふ」があるが意外とここまでは習ったり習わなかったり・・・。何気に生徒たちに「けふ」「てふ」を含む百人一首を数枚配りノートに現代仮名遣いで書かせたところ「けう」「てう」という表記が続出。皆「ハ行」を「ワ行」に置き換えることをきちんと覚えており、それは流石というべきなのだが。実は「けふ」「てふ」の正しい読み方は「きょう」「ちょう」、つまり母音が「エフ」は「ヨウ」となることを説明しこれから春になるとチラホラと見かける「蝶」を歴史的仮名遣いで表記すると「てふ」となることを説明。←かなり生徒たちはひいていた(苦笑)今後はこのブログを読んだ方々も「蝶」を見かけると心の中で「あ、『てふ』だ」と思っていただけると幸いである!?ちなみに「蝶よ花よ(蝶よ花よとは、親が子供をこの上なく可愛がり、大切に育てるさま。)」と言う言葉があるが、そこから転じて「ちやほや」という言葉が出来たらしい。
2016/03/31 09:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
虫
3月上旬の頃を「啓蟄」といって、冬ごもりしていた虫たちが穴からはい出てくることを言うが、北海道はまだ雪が積もっている頃。だが、3月下旬ともなると本州に遅ればせながらも雪がとけて虫たちが元気になる頃か。さて、日本語には・虫の居所が悪い・腹の虫が収まらない・虫が好かない・虫酸(虫唾)が走る・虫の知らせ・虫が起きる・虫が収まらない・虫を殺す・虫を起こす・疳の虫・泣き虫・弱虫・本の虫・芸の虫・虫がつく・虫の息・・・・と例を挙げると枚挙にいとまがないぐらいに「虫」のつく言葉が多い。虫は昔から「見た目」などから皆に忌み嫌われていたから、あまり良くない意味の言い回しが出来たのだろう・・・と安易に考えていたが本来は「昆虫」とは違う「虫」の意味。江戸時代の初期ごろから、「三尸(し)九虫」といって、人の体内には九つの虫がいて、それぞれが、病気を起こしたり、心の中の意識や感情を呼び起こすのだと広く信じられていという。医学も大脳生理学も心理学も発達していなかった時代なので、心の変調や自分でも制御できない心や複雑な感情を説明するために虫の存在を考えたようだ。つまり、体内の「虫」は季節に関係なく活動する。体内の虫の活動を適度に抑えつつ春を迎えたいもの。
2016/03/30 23:32
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です