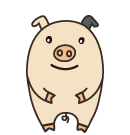小さな国語塾のつぶやき
似ている、共通点
大学4年生時の就職活動時の面接会場で知り合い、以来、仲良くお付き合いをしている友人から久々にメールが。その内容は「俳優の○○がドラマに出ているのを見てると、ん十年前のリクルートスーツ姿のあなたにそっくり!懐かしかった~」というもの。かなりのお世辞が混じっているのは分かっているが、自分よりもかなりかなり見た目が上の人に似ていると言われるのは久しぶりで本当に嬉しかった。日ごろは「え??」という人に似ていると言われ、ショックを受けるのだが(苦笑)。さて、人間は長年の経験から初対面の人を「きっとこんな人だろう」と判断し、その判断基準は自分が今までに知り合った人との共通点。無意識に探した共通点から、目の前の人と自分の相性を瞬時に判断しているものだが、意外と当たると感じている。さて、国語の読解においても似たようなことが言える。他科目と違い「全く同じ問題が出る」と言うことはまずないのだが、文章の構造など結構共通点がある。それに気付き、正しい解き方をすると自ずから正解にたどり着く。共通点を瞬時に見つけるための訓練をしようと思ったら膨大な量の問題を解かなくてはならないか?となるが、そうしなくてもいいようにピンポイントを授業で紹介している。
2016/04/22 12:30
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
類は友を呼ぶ
「人は自分の身近な5人を平均した人物である。その人が、どういう人であるかを知るには、その人の家族や友人など、その人がよく接している人たちを調べればいい、類は友を呼ぶ」という文面を、某心理カウンセラーのブログで見つけた時には思わずドキリとした。どんな人でも3年以内には周囲の人間の何人かが入れ替わるもの、そのことによって自分が成長できている場合もあれば逆に全く成長していない場合もある。果たして自分はどちらか?と自問自答してみた。幸いなことに国語塾を始めてから今でちょうど3年目。正直に言うと、とっても素晴らしいやる気のある生徒さんが継続してくれ、さらには新規の生徒さんも本当にやる気のある、「伸び」が期待できるタイプばかり。逆にそうではないタイプはというと自然に?!ご縁がなくなっていった。プライベートのお付き合いでも、①クリエイティブな方面で新たに一歩を踏み出した②秋ごろに初の本を出版することになった③小説部門で南日本文学大賞を受賞した・・・などなど友人たちの活躍が目覚ましい。自分自身も少しは成長している証拠か?とはいえ彼らに置いていかれないように自分もますます成長しようと日々研鑽。昔の人は良く言ったもの「類は友を呼ぶ」と。一度、自分の周囲を見渡してみて益々の自己研鑽をするにはちょうどいい時期か。
2016/04/21 12:57
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「論文の教室」
同業者のブログ、国語に関する新刊本チェックなどはすっかり習慣になっているのだが、参考になる時もあれば全く収穫なしの時もある。下手すると最初の2行ぐらいで読むのをやめることも。さて、そんな中、久々のヒット本を見つけたので紹介する。「新版 論文の教室 レポートから卒論まで」(戸田山和久著 NHK出版)。タイトルからも分かる通り、小中学生よりももう少し年齢層が上の読者を対象としているが、何ページかは小中学生でも十分参考になりそうなので随時必要に応じて皆に紹介しようと思っている。さて、なぜこの本がおすすめか?①対話形式で良くない論文を添削していく過程が示されている②著者は「型」の重要性を述べており、本書そのものがきっちりと「型」にはまっている。という2点の理由が挙げられる。特に、②に関しては見事というほかはない。「型」が大切だと言っている人間が書く文章がバラバラというのは、まさに「医者の不養生(口では立派なことを言いながら、行動が伴っていないこと)」に他ならないので。自戒を込めて。
2016/04/20 14:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
徒然草はノウハウ本?!
久しぶりに吉田兼好の「徒然草」を読み返したところ、面白い!むろん、中学生の頃に読んだ時は必死で「とにかく現代語で内容を把握して入試に備えなくては!」という想いばかりで、楽しむ余裕なんて全くなく、大人になってから読み返しても当時は今より若かったのでいまいちピンと来なかった。「徒然草」は同じ鎌倉時代に書かれた「方丈記」「軍記物」共にテーマは「無常観」と位置づけされているが・・・言い方を変えると「生き方ノウハウ本」か。つまり、この世は無常(はかない)だからこそ、今を大切に生きるべきであり、その方法は・・・を示唆しているように感じる。本屋さんのビジネス書コーナーに高く山積されている「生き方ノウハウ本」よりもよっぽど具体的ながらも簡潔で分かりやすいかも?!例えば78段では「事情通を気取らない」85段では「真似して学ぶ」187段では「プロとしての心掛け」がテーマとなっている。他の段も「成程・・・」と思わずうなってしまう内容が多く、800年前に既にこういった考え方をしていた先人がいたとは!と新鮮である。古典=古臭くて難しいという先入観をとりあえず横において、試しに読んでみると新しい世界観が広がるだろう。
2016/04/19 14:21
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
向上心
新学期が始まって2週目、少しずつ生活のリズムが整いつつある頃だろうか?さて、中学生ではこの時期になると「希望校調査」があり、「行きたい高校」を書くか「行ける高校」を書くかを迷う人もいるだろう。個人的には「下げるのはいつでもできる」ので今はとりあえず「行きたい高校」を目標設定としてその目標に少しでも近づくように努力すべきだと思う。今の段階で「行ける高校」を書いたとしたら・・・下手すると安心感から勉強へのモチベーションが下がり、成績が下降し「行けるはずの高校」が「行けない高校」になってしまう可能性も。このブログを書きながらふと次のような諺が頭に浮かんだ。「鶏口となるとも牛後となるなかれ(大きな集団の中で尻にいて使われるよりも、小さな集団であっても長となるほうがよい。)」「寄らば大樹の陰(頼りにするのなら、勢力のある者のほうが安心でき利益もあるということのたとえ。 )」この二つは相反する意味を持つ諺で、進学について当てはめてみると前者のように、学力において少し余裕のある学校に進学した方が推薦入試などを受けることが出来て有利かもしれない。とはいえ、少々背伸びをしても少しでも学力の高い高校に進学した方が、環境が整っており将来的に有利かもしれず、どちらがいいかとは言えず人それぞれか。ただ、先にも書いたように前期始まったばかりの今はとりあえず後者の「寄らば大樹の陰」を目指して向上心を保つべきではないか?
2016/04/18 21:40
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
夢の影響
昨日か今日にかけて、睡眠中に久しぶりに仕事についての「良い夢」を見た。毎日夢を見ているのだが、良い夢は一瞬にして忘れてしまい、良くない夢だけはしっかりと覚えている。仕事に関しての良くない夢と言うのは、全く知らない子供たちを相手に国語授業をしており、当然全く授業が成り立たない・・・といった内容がほとんど。でも今回の夢は「現在通って来てくれている生徒さんと共に楽しく授業を行っている」という内容。ホッ。さて、夢とは昔から不思議なものとして小説の題材に用いられたり、下手するとその人の人生に大きな影響を与えたりするもの。国学の研究者として江戸時代に活躍した平田篤胤は、夢の中で本居宣長と師弟の関係を結んだと主張。宣長と同じ時代(江戸)に生まれながらも、宣長に会えなかったことを悔やんでいたところ先のような夢を見たという。夢の中で宣長先生に会ったというだけではなく、夢の中で宣長に弟子入りを許され師弟の関係を結んだと主張するのだから恐れ入ったもの。本当に弟子入りを許されたかどうかは、現世での目撃者がいるわけではないので実証しようがないのだが、それでも篤胤が「自分は宣長の弟子だ」と主張し、国学を「復古神道」の域まで押し上げる役割を担ったことは動かない事実。たかが夢と侮ること勿れ?!強い意志があれば夢からヒントをもらえ、それが今後に良い影響を持つことがあるのはどの分野でも、起りうる。一番有名なのが湯川秀樹博士の「中間子理論」か。さ、自分自身も良い夢を見たことをきっかけに今後ますます精進。
2016/04/17 14:13
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
役目
指導者の役目とは、まずは「勉強を教える」こと、「勉強を教える」ことと同じぐらいに「生徒のネガティブな思い込みをなくす」ことが大切な役目ではないか?と思う今日この頃。昨日、教室に入ってホワイトボードに書かれている内容を見た瞬間に「え?今日はもしかして古典?無理無理無理~~~!難しい~~~」と言った中学生のS君。漢詩について分かりやすく?作った資料を配ったのだが、それを見た瞬間にも「難しそう!」の一点張り。そこで「今日、学習することはここに書いてある3つ。一つ目は少し面倒くさいけれど、慣れると簡単に感じるよ。二つ目と三つめは超簡単!じゃあ、試しに三つ目からやってみよう」と声掛けをして授業に入ったところ・・・。とにかく素直なS君は「あれ?本当に簡単だ、なーんだ!意外と面白いかも」と黙々と演習に励んだ。むろん、演習問題はほぼ完ぺき!思わず気を良くして「ほら~、国語って簡単でしょう?ほかの科目よりもよっぽど簡単で、同じ『語』のつく英語と比べると断然国語の方がやりやすいでしょう?」と言うと、英語が大の得意のS君からは「英語の方が簡単です」とバッサリ!それでも少なくとも「難しい」が「ムズ…」ぐらいにはなったようでホッ。苦手意識を持っているとなかなかやる気が起きない➡勉強しない➡ますますできなくなるという悪循環。その悪循環をを好循環にするためのきっかけづくりの手助けをさせてもらうべく日々精進。
2016/04/16 04:29
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
漢文
中学生にとって、古文と漢文だと漢文の方が簡単だという意見が多い。なぜか?古文は覚えるべき単語が多くて大変だから・・・・。だが、そうはいっても漢文も現代文とは意味が違う単語がいくつか存在するので頑張って覚える必要がある。例えば、漢文で「故人」とは「親友」と言う意味で、決して「亡くなった人」ではない。昨日、中学生クラスでは有名な漢詩「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る(李白)」を学習したが「故人」を単純に「死んだ人」と解釈してしまったため、問1「誰が見えなくなったか」で既にパンク。さらには「楼(ろう)」の意味が分からないので情景が全く頭に浮かばない・・・。「楼(ろう)」とは①高い建物②遠くを見るために作られた高い建物、と説明し絵を描くとようやく納得。←絵と言うよりも棒人間を描いただけのピクトグラム状態で生徒さんには申し訳ないことをしたが。新しいこと、しかもあまり馴染みがないことを覚えるのは大変だが、意外と馴染みがないと思っている事柄でも身近なところで目にすることがある。例えば帯広の有名な中華料理屋さん「美珍楼(みちんろう)」には「楼」という字が使われている。日本では「~屋」となるであろうところ、中華料理のお店なので「~屋」とはせずに「楼」としたのだろうと推測すると漢文や漢詩が楽しくなる?!
2016/04/15 14:00
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
正しい学習法
昨日、中学生が体験授業を受けてくれ、入塾するかどうかはともかくとして、その子を見てて思ったことが一つ。この子は伸びるだろうなああと言うこと。それはなぜか?「なぜその答えになるか?」と必死で考えて、納得したことを身につけようとする姿勢が素晴らしいから。国語だけがとにかく苦手!とご連絡を頂き、どの程度苦手なのかは分からないまま、とりあえず体験してもらうよう提案して迎えた昨日。確かに一つ一つじっくりと解くため時間はかなりかかるのだが、それに関しては解き方さえ身につけて慣れると時短は可能。伸びるためには①解き方をマスターする②①+「なぜその答えになるか?」を納得し、究極は説明できるぐらいになること、という2点が重要。逆に言うと自力で「国語が苦手だから、取りあえず沢山問題を解けばいいんだ!」とばかりにやみくもにひたすらひたすら問題集を解いて、答えを写して終わり・・・だといつまでたっても成績の伸びは期待できない。それは他の科目にも言えることだろうが・・・。伸びるためには「ヤル気+正しい学習法」が大切だとつくづく感じる今日この頃。
2016/04/14 10:43
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
記述問題・・・
「記述問題は採点者によって基準が変わるので注意!」これを読むと「え?」とびっくり(@_@)するかもしれないが、基本的には、ある一つの試験、テスト、入試では同じ人間が採点するのでご安心を。同じ解答に対して他の人が正解で自分だけが不正解ということは起こらない。ではどういうことか?①自分では「書けた!正解」と思っている解答が不正解になることがあるということ。②「いつ、だれが、どこで、何を、どうした」を意識して書くこと、この二点をしっかりと肝に銘じる必要がある。以前、ある生徒が「先生!理科の学力テストの記述、ヤマをかけたら当たってました~。見て下さい、正解しました」と喜んで解答を見せてくれた。そこには「問 炭酸水素ナトリウムを加熱するときに、なぜ試験管の底部を上げるのか?」「生徒の解答 逆流を防ぐため」とあり、しっかりと丸がはいっているのだが・・・思わずその解答を見た瞬間に固まってしまった。「え?よくこれで丸をもらえたね。今回はたまたま丸をもらえたけれど、採点者によってはこれは×か△だよ。主語がない!何の逆流を防ぐの?正しくは『発生した水が逆流して試験官が割れるのを防ぐため』だよ。これは丸暗記!!!」と思わず鬼の形相で延々と諭した。逆に、こういった解答をしたため×だった・・・という生徒も少なからずいる。国語の限らず、記述は先に書いた二点の基本をしっかりと守ること!
2016/04/13 12:58
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です