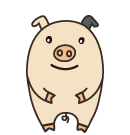小さな国語塾のつぶやき
古文の「」
古文で、よく聞かれる代表的な問いは二つあり、一つは動作主、もう一つは会話文を抜き出すという問題。以前に、同じ動作主の場合は「~て、~て、~て」となると紹介したので今日は会話文について。古文では現代語と違って「」というものがなく改行もされておらず、中学校で習う代表的な見分け方は「文末が『と』で終わる部分までが会話文」」という内容。むろん、それは正しく「と」の後に「言ふ」「曰く」と続くことが多いため分かりやすい。そのため、大半の中学生は会話の終わりは間違いなく抜き出せるのだが・・・・、問題は会話のがどこから始まるか?!内容から考えないといけないのだが・・・・時々「○○言ふには・・・・・・と言ふ」のように「言」が2回書いてあることがある。この場合は超ラッキーで「言ふには」の直後「・・・・・・」が会話文になる。つまり現代語の「」の代わりに「言ふ」という言葉で会話の内容を挟んでいるのである。この形に慣れるまでは「言う」が2回もある!一体どこから会話文?!となるのだが、先にも書いたように「言う」は「」の代わり!と認識して割り切って覚えると正答率がアップし、しかも楽しくなる。昔の人の気分になってぜひ古文の決まり事を覚えてみると世界が広がること間違いなし。
2016/03/29 17:49
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「ヤル気」+「本気」
今日は一気に春が来た!といった陽気で気分が高揚する。春というと時期は気分が高揚し、新しいことを始めたくなる時期だからだろうか?昔から多くの諺や言い回しが作られている。そのうちの一つとして「春植えざれば秋実らず ( はるうえざればあきみのらず ) なんにもしないのによい報いを期待してもだめである。春には必ず種をまくのは鉄則である。 原因のないところに結果があるはずがない。」がある。ただ単に「ああしたい、こうしたい、こうなればいいなあ」と思っているだけで動かないと、結果が出るわけがない。よく「4月から頑張ります!」と、とりあえずヤル気を宣言するというパターンが多いが、宣言するだけでなく実行しなくては意味がない。むろん「別に~、新年度だからと言って何も変わらない。。。。」とふてくされるよりは「頑張る」とヤル気を宣言する方が立派であるが、その「ヤル気」に「本気」という息を吹き込むことをぜひとも実行してほしい。つまり「ヤル気」だけでは結果はついてこない、「ヤル気」と「本気」という二つの気持ちがそろってこそ秋に実がなるのである。まさに春に種を植えたけれど(ヤル気)そのまま放っておいてはいけない、水やりや肥料(本気)が必要。自戒を込めて。
2016/03/28 14:51
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
能動的に暗唱する
哲学者のフランシスコ・ベーコンは、1620年にこんな言葉を残した。「本の一節を暗記したいなら、20回読むよりも、暗唱を試みて思い出せない時に本を開くということを織り交ぜながら10回読むほうがいい」。国語では有名な古文の冒頭部を暗唱というのは中高生泣かせの課題。「祇園精舎の鐘の声・・・」で始まる平家物語、方丈記、徒然草、奥の細道・・・などなど大半の中学校で暗唱テストが行われる。その時にぜひとも実行してほしいのが先の方法。書いたり読んだりすることはもちろん大切だが、とにかく「どの程度覚えているか」を人に聞いてもらう、あるいは自分で暗唱してみて随時確認することが最も重要。やってみると分かるが、「暗記」を意識しておかないと「ただ、読むだけ。ただ書くだけ」という受動的な行動になってしまうのである。そうではなく「思い出そう」と意識する、時間を空けて自分でテストをするという能動的な繰り返しが効果的。そういった能動的な動機づけとして暗唱テストがあるのであって・・・生徒泣かせだが、中学生の知識を確かなものにするための最善の方法だと思う。もう一度言う。何かを覚えようとする時は「能動的」を意識すること!
2016/03/27 17:21
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
覆水盆に返らず
古文問題集を解いていると、中国の故事成語の元となった話が載っていることがある。読み進めていくうちに「あ、あの話だ」となり、ワクワクするのだがそれは故事成語を知っているから。故事成語を知らない状態だと、単に「難しい古文だなあ、つまらない・・・」となってしまう。逆に故事成語を知らなくても、実は今読んだ話から故事成語が出来たと知ることが出来れば「一粒で二度おいしい」となる。残念ながら、どの問題集にもなぜか「ここから『・・・・』という故事成語が出来た」という解説が載っていない。不思議で仕方がないのだが、まあ載っていないものはしょうがないし、詳しい解説をするのが国語塾としての仕事なので喜んで皆にお伝えしていく予定。ちなみに近々、生徒たちに演習+故事成語の紹介予定の作品は「覆水盆に返らず」と「人間万事塞翁が馬」。今、この二つの故事成語をこうしてブログに書きながら次のようなことを考えた。本当に人間の幸不幸は分からないもので、失敗した~もう取り返しがつかない(覆水盆に返らず)と思ったとしても果たしてそうなのか?こぼした水を元に戻すことは確かに出来ないが、それならば新しい水を注げばいいのではないか?そうすると不幸だと思ったことが実は不幸ではなくなるのでは?逆に幸福!だと胡坐をかいていてもいけない。ただ、一つ言えることは「やらずに後悔」するよりも「やって後悔」する方がいいかなあと。
2016/03/26 16:18
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
我(が)を持つ
日本はダジャレ(掛詞…一つの言葉に二つ以上の意味を込めること)の国だなあとつくづく思う。例えば、神社への砂利石は 邪気を離(り)、離す!と言われていたり、神社の奥にある鏡は か:が:みの 真ん中のが:我(自我)を取って、神になる・・・と言ういわれがある程。真偽のほどはともかくとして「我」があるから人間なんだというのは納得。さて、では「我」は良くないのか?というと決してそう言うわけではない。強すぎると「我がまま」となるが、程よい「我」は個性となり、また「我」があるからこそ人間は頑張れるのだ。人間は、我(自分)が少しでも快適に、よりよくなるために、目の前の不便さ不具合を何とかすべくして工夫するもの。先日、某人から「高校1年生になる子供が全く勉強しなくて困っている。」と相談を受けたが、困っているのは親だけであって実は本人は全く困っていないのである。だから勉強しないのだ。昔とは違って、今の子は住むところや今日食べるものに困っているというわけではなく、テストで悪い点を取ったからと言って明日の食べ物がなくなるわけではない。せいぜい親や先生から口うるさく言われるだけなのだ。恵まれていることは素晴らしいが、恵まれすぎると工夫をしなくなる・・・。いい意味での危機感や困った状況を作る(具体的にはピリピリした環境の塾に入れるなど)、我(が)を持つことも時には大切か。
2016/03/25 00:26
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
若いうちに
よく、なぜ学校のことをしないのかと問い合わせを受けるが、当国語塾では基本的には学校で学習する内容はやっていない。なぜか?教科書以外の、どんな問いにも対応できるような力を生徒たちに身につけてほしいから、敢えて生徒たちにとっては「初見」の問題集やプリントを解かせている。「学校のテストはよくできるけれど、校外模試や学力テストでは全く・・・・。」というのはよくあるパターン。誰にとっても初めての問題は難しいため、公開模試や学力テストの方が平均点は低くなる傾向がある。ということはいわゆる「初見」の問題を解けるようになっておけば国語でかなりの点数を稼ぐことが出来るのである。また、初見の国語の問題を解く訓練をすることによって、将来的に色んな書類や本を読むときにスムーズにそれらに対応できるようになる。自転車の乗り方と同様、一度身につけたスキルは勘が鈍ることは有ってもなくなることはない。若いうちに出来ることはなんでも挑戦して身につけておいて損はないと思う今日この頃。
2016/03/24 15:09
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
春休み
いよいよ、あと2日で春休み・・・。春休みは学年が変わる前の休みと言うことで基本的には学校の宿題がないので、次の学年に向けての準備をする絶好のチャンス。そんなことは言われなくても皆分かっていることだが、気がつくと何もせずに終わってしまったということがしばしば。では、何をやればいいか?国語に関して言うならば①現学年の漢字復習②苦手分野の克服の2点につきる。現代文、古文、漢文に分けてさらに現代文を「説明文、随筆、小説」の三つに分類。その中で苦手な分野を中心に学習するとよいだろう。特に苦手分野はないならばそれにこしたことはないのだが、もしも苦手分野があるならば、ただやみくもに問題集を解いて仕上げる・・・のではなく苦手分野に絞って集中学習した方が効果的。説明文、随筆、小説、漢文、古文、それぞれ特徴や解き方のコツ、パターンがあるということは繰り返し授業でプリントを配布したり説明したり演習しているので、それらを使いながら復習するとよいだろう。国語がすべて苦手で、新年度から何とかしたい~という方はぜひ国語塾の門を叩いてほしい。新規塾生募集中!
2016/03/23 10:46
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
説明できるかどうか?
当たり前のことだが、今こうしてブログを書くためには①パソコンの電源を入れる②パスワードを入れる③HPを開く④またパスワードを入れる・・・という作業をすることによってブログページを開き、執筆できる。この行程の一か所でも抜けたり、順番を間違えるとブログを書くという作業は出来ない。同じことが国語の問題を解く時にも言える。解き方や論理の方法を間違えると正解にたどり着かないのである。とはいえ、ついつい「なんとなく」で答えを選んでしまいがちで、しかもそれがたまたま正解だったということもあるため、なかなか「論理的に」「正しい解き方で」と言っても子供たちはなかなか実感や実行が出来ない。先週、某生徒が4択の問題を見てパッと答えを選んだのだが・・・思わず「なぜ、それが答えになる?」と突っ込んだ。実は最初は直感で選んでいたようだが、じっくりと文章を読んで考えた末に「○○で、△△だから」と答え、たまたま選んだ答えが正しかったことを自分で理解し納得した様子。なぜその答えになるか?を説明することを意識するとかなりの国語力がつく。
2016/03/22 11:26
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「いけい」と「いぎょう」
正直に言うが、自分自身はあらゆる点でかなり個性的(変わっている)と自覚がある。そのうちの一つとしては、類まれなる体力を持っていることで、保育園~高校卒業まで一度も病気などになったことがないため欠席はゼロ、いわゆる皆勤である(大学はやたら自主休校が多かったが)。自身のような個人事業主にとっては体調管理は不可欠なため類まれなる体力を保持することはかなりの偉業(いぎょう)だと思うが、逆にこのようなタイプの人間が、例えば医療従事者となった場合には患者さんの気持ちが分からないという事態が起こりうるので、体力がある=善、体力がない=悪とは必ずしも当てはまらない。さて、他の部分でもかなり個性的なため友人が畏敬(いけい)の念を込めて素敵なニックネームをつけてくれているのだが自分としては「畏敬(いけい)」どころか「異形」の方がピッタリかも?と思っている。パソコンで「いけい」と入力すると「畏敬、異形、異型、池井・・・」とヒットし思わず笑ってしまう。ちなみに「異形」の正しい読み方は「いぎょう」。今度は「いぎょう」とパソコンに打ち込むと「偉業、異形、易行・・・」とヒット。パソコン普及のため自分では漢字を書かなくなり、漢字力がつかなくなると言われているが、逆に言うとパソコンのおかげで読みを1つ入力するだけで沢山の漢字がヒットし、多くの漢字を知ることが出来る。目的の漢字のみならず他の漢字の使い方などもついでに?学習する良いチャンス。
2016/03/21 03:09
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
儲
お商売をやっていく上では「儲け」を意識することが大切。なぜか?きれいごとばかりではやっていけず、いずれ「儲け」を意識しないと仕事としての体力が続かず、長くはやっていけないから。「儲」と言う字は、よく「信+者」と解釈されることが多く、昨日の朝日新聞紙上においても某経営者が「儲けとは人を信じることです」と述べていた。が、実は「儲」という字はもともとは形声文字(人+諸)。「横から見た人」の象形と「もろもろ(多くの)」の意味だが、ここでは「貯」に通じ、「たくわえておく」の意味)から、「跡継ぎとして備えておく人」、「皇太子」を意味する「儲」という漢字が成り立ったという。確かに儲ける為には「知識、お金、その他もろもろのものを蓄えておき、なおかつ人を信じてこそ初めて成り立つもの」だと最近感じる。昔の人の知恵はは素晴らしいなあと感心するとともに、教室開講3年目の自分自身への戒めも込めて「自分自身もっともっと精進して沢山の知識などを蓄えて、よりよい授業をしつつ、生徒を信じ、なおかつ信じてもらえるよう」に頑張ろうと思う今日この頃。
2016/03/20 14:59
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です