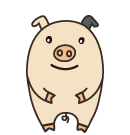小さな国語塾のつぶやき
対義語
中学生クラスでは引き続き「対義語」演習。カードを使って組み合わせを見つけたり、実際の入試問題を解いてみたり・・・。入試問題では「相対」の対義語「絶対」の正答率がたったの6パーセントだったというデータに、皆びっくりすると同時に自分達は「出来た~」という達成感を味わいつつ、頑張っている。むろん、どの生徒も最初からすべての対義語を覚えているわけではなく、カードとにらめっこしながら「ウーン。『相対』には『対』がつくから同じく『対』のついている『絶対』を選べばいいのかな?『必然』も同じく『然』を探そう!」と言った具合に取り組みつつ、正しい答えを導いている。そう、実は対義語とはコインの裏表状態、つまりは切り離すことができないペアなので、同じ漢字を含む場合が多くなる。つまり片方だけで存在することが出来ないのであり、両方大切な概念。「手段」の反対は「目的」なのだが、なぜそれらが対比になるのかがピンと来なかったw君。目的を最終ゴールとするならば、そこに至るまでの過程が手段、つまり「手段」と「目的」は一続きのもので、指す場所が違う・・・と図を書いて説明するとようやく納得。「対義語」=「反対、完全にかけ離れた」と思い込んでいたようだ。「対義語」を覚えて、さらには使えるようなるためには、相当の練習が必要だがその努力に見合うだけの知識、概念等が身につくのでぜひ皆にマスターしてほしい内容。
2016/05/12 13:46
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ペン(本)の力
「ペンは剣よりも強し」という有名な格言がある。【意味】ペンは剣よりも強しとは、言論の力は武力よりも大きい力を持っているということ。イギリスの政治家・小説家ブルワー・リットンの戯曲『リシュリュー』にある「The pen is mightier than the sword.」の訳。これは、「言葉の武力に対しての影響力」をメインで語っているが・・・・個人的には武力のみならず、「口で言う」よりも「ペンで書いたもの(本)」は影響力が強い!ということも言えるのではないか?と感じる。どういうことか?相手に対しての言葉がうまく見つからない時や、言っても聞き入れてもらえない、下手すると誤解を招く・・・という場合には、おすすめの「本」を贈ることが意外と有効だということ。「本」を贈ることのメリットは相手が「何度も読み返すことが出来る」「知らない人(←大半はそうだろう)、専門家が書いていることなので客観的に読むことが出来る」。場合によっては「何書いてるの?この人・・・」となることもあるだろうが、むろんそれもOK!実は先日、叔母が亡くなり、叔母の実姉である母があまりにも落ち込んでおり、かける言葉が見つからなかった。ただ、そばにいてあげたい・・・と思いきや遠距離のためそうもいかず。そこで、某本を何冊か贈ったところ喜ばれたという次第。「ペン」「本」の力侮ること勿れ。
2016/05/11 11:45
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
試され事
10日ほど前、中学3年生男子から「先生って、(本当にいい生徒に囲まれて)幸せなんですね!」と言われ「(目の前の君も含めて)本当にそうだね。みんな素晴らしい子たちばかりで」と答えた。むろん嘘偽りなどなく答えたのだが・・・・。先のように自信を持って言えるのは「天からの?!試され事を沢山たくさん経験中だから、実感できるんだよなああ」と心の中でつぶやいた。昨日のブログでは「頼まれ事は試され事?!」というタイトルで、思い切り持論を展開したが・・・・、目に見える人からのダイレクトな頼まれ事は拒否することが出来ても人知を超えたもの?や出来事等によるアクシデント(ある人曰く「天からの試され事」と)は避けたくても避けることが出来ない。うまく避けたように思えても、それらのいわゆる「失敗」と思えるようなことを1つ1つ乗り越えていかないことには別の形でのアクシデント、修行?!が勃発。成功した人、成功してる人は間違いなく「多くの失敗」を乗り越えてると思う。仕事、勉強においては近道はないが逆に言うと正しい努力をしていれば実を結ぶということか。さ、今週も明日からの授業に向けて楽しく今から準備予定!!!
2016/05/10 13:11
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
頼まれ事は試され事?!
「頼まれ事は試されごと」という言葉について、正しい意図を次から選べ①「頼まれ事」が増えるということは、自分を成長させる試験。無理してでも引き受けること②「頼まれ事」が増えるということは、自分が成長している証拠。内容がお互いにとってプラスになることならば頑張って引き受けた方がいい③「頼まれ事」が増えることは、自分の成長においてプラスだが相手にとってはマイナス。相手には人を頼らないよう説得する方がよく、「断る力」を持ってるかどうかの試験である・・・・。①~③のうち正解は②。かなり迷ったと思うが?「頼まれ事は試されごと」とはいわゆる「成功者」と呼ばれる人たちが口々にするフレーズ。本屋さんに山積みのノウハウ本やカリスマと呼ばれる人のセミナーなどでは語りつくされている。が、ここで怖いのが、真意を間違って捉える人が多く①だと思い込んで必死になって何でもかんでも引き受けて「自己啓発」どころか「自己破壊」にまっしぐらの人が世の中に多いこと。例えば「自分は勉強が苦手だから、替え玉受験をしてほしい」という依頼を引き受けるか?と聞かれるとほとんどの人は「No!」と言うだろう。このように、明らかに常識外れのことに対しては流石に拒否するものの、あやふやな?ことに対してはあまり熟慮せずに「引き受けなくては」という強迫観念に駆られる。ちなみに国語の選択問題では「極論は×」という暗黙のルールがある(以前にもブログで何度か紹介)。となると…①は×。国語力をしっかりと身につけて駆使することこそ、本来の「自己啓発」にほかならない。
2016/05/09 10:02
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
飽き
いよいよゴールデンウィークは今日で終わり。人によっては10連休と言う人もいただろうが・・・、ゴールデンウィーク明けになると話題になるのが「五月病」。「五月病」とは正式な医学用語ではないが「環境の変化」が起こすストレス状態のこと。程度は様々だが、やる気が起きない、考え事や集中ができない、身体がだるい、頭痛や腹痛がする、遅刻する、食欲が湧かない……等の症状が現れる、新年度から新しい環境になった人がかかりやすいと言われる。何気にパソコンに「五月病」と入力しようものなら、これでもか~というぐらいに「原因」「対処法」などなどまことしとやかに書かれている。対処法を読むと、成程~と思わせるような理想的なことばかりが書かれているが、それらを守れるぐらいなら最初から五月病なんてかからない。下手に対処法を読んで実行しようとすればするほど「ああ、守れなかった。出来なかった。自分はダメだ」とますます落ち込む原因になりかねないのでは?とツッコミを入れたくなる。ではどうすればいいか?敢えて日ごろと違う行動をとることが有効では?と思う。なぜなら、人が無気力状態になる大きな原因には“飽き”があるから。最初はやる気を持って取り組んでいた作業だからこそ、飽きがきやすい、という傾向もあると言われている。そんなわけで、先月末から今月にかけては少し「緩め」「いつもと違うパターン」のこと(例えばカード、テキストを使わずに発想力を養う訓練、なぞなぞ形式のヒアリングなど)をと心がけているが果たして効果はいかに?少しでも「飽き」がこないよう、あれやこれやと計画中。
2016/05/08 04:59
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
古典こそ、客観的に
古文で「~はなぜか?本文中から抜き出しなさい」という問題で引っかかった中学生。答えは「今にも死なん(今にも死にそう)」(だから)という短い文だったのだが、「理由」を答えるのだからおそらく長めの文だろうと思い込んだ結果、間違ってしまったようだ。現代文はもちろん、特に古文では「直接的な表現」を探すことが大切。決して文章の長短ではない。また、別の中学生は「塞翁が馬」という故事成語の元となった逸話を扱っている古文を読んだ時に、無意識に主観で解いてしまい撃沈。一般的には不幸があったら悲しみ落ち込んだりする、逆に幸せなことがあったら喜ぶが・・・。古典、特に教訓めいた話では「実際には有り得ないこと」が題材になっている。現代文の小説、しかも中学生が主人公の場合、いかにも「有りそうな」作り話だが、古典は全く違う。動物がしゃべるのは日常茶飯、下手すると異形の物まで登場する。つまり現代文以上に「主観」を捨てて、あくまでも本文を客観的に読むことを意識することが大切!さらには、「ん?」という内容であっても主題は人道的なことが多いことも念頭に入れておくと「幽霊、魂」が出てきたからといって四択で主題を選ぶ時に「怪談話」と選ばずに済む。
2016/05/07 04:19
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
マイナス思考
「人間の思考は8割がマイナスである」ことは心理学では良く言われる。元テニスプレーヤー、現スポーツキャスターの松岡修造氏も経験上から全く同じことを言っている。確かに、気がつくと悪い方向へと考えてしまうのが人間であり、それがダメかと言うと決してそうではない。「こうなりたくない、こうなったらどうしよう」と思うから、それに対しての策を練ることが出来るから。とはいえ8割が行き過ぎて10割…ともなろうものなら生きていくのが辛くなる!偉そうに言っている自分自身はというと、有難いことに「考えるべきこと≒やるべきこと」が多いためマイナス思考が入ってい来る余地がない!例えばこの2週間ほどは、古文のコツをどんなふうに一枚の用紙に分かりやすくまとめるか?!と、ああでもない、こうでもないとデザインを常に考えている。むろん他にも次の授業は○○にはこの資料を使って△△にはこちらの資料で・・・と考えることが楽しくて仕方がない。本当に生徒さん達のおかげだと日々感謝。話を元に戻すと・・・・、勉強でも同じで、ただ単に漠然と机に向かったり通塾してるだけだとマイナス思考全開で楽しくないが、ちょっとした目的(例えば、国語塾のクジであたりを出す!でもOK)を持つだけで楽しくなり、しかも教わったことが身につき成績アップにつながらる。よくあるパターンが「○○先生がカッコイイから、国語を頑張る~」というタイプの女生徒の成績がアップすること。残念ながら、当塾に関しては「先生のために~♡」という生徒は皆無だろうが、だからこそ少しでも魅力ある授業にしようと日々楽しみながら思考中。
2016/05/06 14:01
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
五月人形
今日は「子供の日」。男の子がいる家庭では「鯉のぼり」や「五月人形」を飾ることも。あるいは本来は脇役であるはずの「兜」を飾る場合もある。武将にとっての鎧や兜は、自分の身を護るための大切な道具だったことから、命を守る象徴と考えられ男の子を事故や病気、災害などから守ってくれますように。という願いを込めて飾るようになったという。また、五月人形といえば、やっぱり「武者人形」、勇ましい男の子に育ちますようにという願いが込められている。が、この五月人形に最近は変化が起きているという。勇ましさが定番だった五月人形、以前は15歳ぐらいがモデルの物が多かったが、夜に見ると子供が怖がる、サイズが大きくて収納に困るという理由から敬遠されるようになり、最近は3歳ぐらいの小さな子供がモデルになったような「可愛い化」が進んでいるという。時代のニーズに合わせて変化することは大切なことだが、言葉同様に、「本来の意味」や由来をきちんと把握しておくことが大切なのでは?と感じる。幼い子供が鎧☞幼いうちから戦闘に巻き込まれる?!と思わず意地悪なツッコミを入れたくなるのは自分だけか?!
2016/05/05 06:35
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
古語
古文で「口惜し(くちおし)」という言葉があり、意味は「残念だ、悔しい」であるが、パソコンなどで「くやしい」と入力すると「悔しい」のほかに「口惜し」という漢字もヒットする。実は「くちおし」は口惜しいの元となった言葉で、「朽ちる(朽ちる、老いる)ことが惜しい」→「口惜し」になったと考えられている。とはいえ、中学生にとっては「口惜し」「くちおし」という言葉を見てパッと「悔しい、残念だ」と答えられるなんてことはまずない。毎回言っているように、古文は外国語だと割り切って、一つ一つの単語や決まりを覚える必要がある。表記が日本語なのでとりあえず音読は出来るが何度も音読したからといって意味が分かるわけではない。地道に一つ一つ単語を覚えていくと、おぼろげながらに意味が通じるもの。現代語は古語が変化しているわけだが、下手すると意味が全く逆・・・ということもありうる。古語から現代語に至るまでの過程や語源を考えると丸暗記するよりは楽に頭に入る。。また、作者が同じ場合には同じ単語を別の話で使うこともしばしば。例えば徒然草では「いやし(身分が低い)」、枕草子では言わずもがな「をかし」など。古典は配点が低い・・・と侮ること勿れ。きちんと努力すると必ず高得点を見込めるのだから。
2016/05/04 09:15
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
細分化⇒組み合わせ
帯広在住の書道家が次のようのおっしゃった。「字を一度すべて分解して、形などをしっかりと練習して覚える。次にそれらをパズルを組み合わせるようにして、はめていく。この時に一か所でもピッタリとはまらなかったら美しいとは言えない、間違った字形」と。成程、確かに・・・。特に漢字の場合は「偏と旁」のバランスが大切だということは素人にも分かる。さて、話を伺いながら「文章・・・美術の世界でも同じことが言える。あらゆることの真理は同じ」と改めて実感。文章を書く時に「型」が大切だということは、小中学生にとってはなかなか実感がわかないため、どうしても「思ったことや感じたこと」を、どんどん文に書いていく。筆が速いことは素晴らしいのだが、果たして出来具合は?と言われると・・・・。「自分の子供は作文や文章が苦手で・・・」とSOSを求められることがあるが、筆が遅いから駄目!なのではない。大切なことは前もっての「準備」。まずはテーマに沿っての内容を細かく分ける。分けた部分について、いくつか文章を作っていく。最後のそれらを組み合わせていくという作業をしていくとコンパクトに収まった分かりやすい内容になっている。授業中内に書かないといけない(スピード重視)などの場合は仕方がないが、夏休みの課題などでは是非じっくりと書きたいことのテーマを細分化して・・・を実行してほしい。それに慣れておくと将来、大学生になった時のレポート、社会人になってからの報告書などにそれらの経験が生きてくる。
2016/05/03 11:17
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です